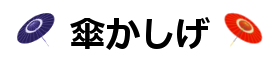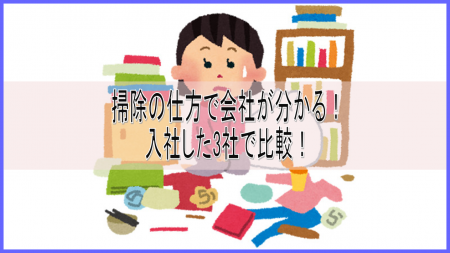捨てる!快適生活

前回、会社での掃除のことを書きましたが、その続編です。
◆前回の記事◆
掃除のパイオニア的な本!(多分)
前回の流れで掃除の良書の紹介をします。
まだコンマリさんも世の中に知られてなくて断捨離という言葉もなかったころの本ですが、多分コンマリさんをはじめ、多くの人に影響を与えた本じゃないかと私は思っています。
私はこの本を読んでからすぐにありえないくらいものを捨てて親に心配されたほどでした笑
でも書いてあることは、感情的すぎず、論理的すぎず、人間らしい(?)ところがいいです。
ここを間違えると「ものがあるだけでストレス」「冷蔵庫もなく懐中電灯で暮らしてる」とかそれはそれで生きるのが大変になるので、断捨離も程よく楽しんでやらないと危険ですからね。
勝間さんとかは大分キテて見ている分にはかなり楽しいです笑
リンクページはちきりんさんの記事ですが、ちきりんさんも「真似したい」とはさすがに書いてないですね。
ちきりんさんと同様に実際に導入したいことは穴空き包丁を使うことくらいですね。
勝間さんとその支持者の方には申し訳ないですが、こうなってしまうと本末転倒です。
1度に作る数と量にもよりますが、片付け、各マシンの通年のメンテなどを含めるとどこまで合理的かもちょっと疑問です。
長期的に見たらメリット(快適さ)よりデメリット(息苦しさ)が上じゃないでしょうか。
もちろん、本人が「そうは感じてない、超快適!」と自覚しているなら何の問題もない話ではありますが、傍目から見ていると以前に書いた電話を激しく嫌う人たちと同じものを感じます。
◆関連記事◆
10年経っても忘れられない良書
読後10年経っても私が覚えている印象に残っていることを挙げます。
- 片付けるとき(例えば本棚)は一度全部出して「また使うか(読むか)」を考えて可能性がないものは廃棄
- 2年以上触ってないものも廃棄
- 捨てなきゃよかったと思うことはまずない
- どうしてもというときは買い直せる
→買い直すことはまずない - 捨てにくいものは写真に収める
→写真を見返すことはまずない。 - 物を置く位置を決めると部屋は勝手に片付く
→爪切りはここ、リモコンはここという具合に - 物を置くのは物に家賃を払っているのと同じ
例えば6畳で6万の部屋に1畳分の本棚を置くということは、本の維持費として毎月1万円払い続けているようなもの
→それに見合うくらいに本を活用しているか
中でもなるほどなぁと思ったのは片づけるまでの回数の話です。
片付けるまでの回数を意識する
例えば、ドア付きクローゼットの中にある衣装ケースにタオルをしまう場合

- クローゼットのドアを開く
- 衣装ケースを引き出す
- タオルをしまう
- 衣装ケースをしめる
- クローゼットのドアを閉める
と、5工程になります。
この数が増えるほど面倒になるので片付けなくなります。
だから、
「日常的に使うものほどこの数値を小さくし、年に数回しか使わないものは数が大きくなるところへしまう」
こうやってものを整理するととても片付きやすいです。
ちなみに、片付けの最強の家具は
- ものを置く
で、終了の「棚」です。
実践してわかったこと
10年間、この本の教え(?)を守ってきてわかったことは「書いてある通り」でした。
買い直したものもないですし、捨てるときに撮影した写真をわざわざ見ることもありません。
物の定位置を「片付けるまでの回数」を意識して決めていくとそれだけでかなり楽に片付きます。
掃除以外の考え方も変わった
たくさんのものを捨ててスッキリすると同じところにまた物を置くことがイヤになり、物を欲しくなくなります。
洋服はその最たるものですね。
こちらの記事で靴下を揃えることを書きましたが、この本の影響かもしれません。
◆関連記事◆
洋服も最小限で良くなり、普段の生活や仕事でも「シンプルに、回数を減らして効率的に」という考え方が軸になりました。
私にとっては単なる掃除の本ではなく、人生に影響を与えた本の1つですね。
考えてみたら、
仕事ができない人ほど滅多に使わない資料をデスクの手の届くところに置いてますからね笑
まとめ
片付かない理由は2つ
- 不要なものが多い
- 物の位置が決まってない
この2つを「人間的に、効率良く」解決する方法が書いてあり、「断捨離」「ミニマミスト」という言葉が市民権を持つ前の本という点も踏まえて、掃除の本質がしっかり書かれた良書です。
・・・そう言えば買い直したものがありました。
この本です笑
BOOK・OFFで安く売っていたので購入して知人にプレゼントしました。
それぐらいの良書です!