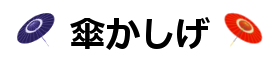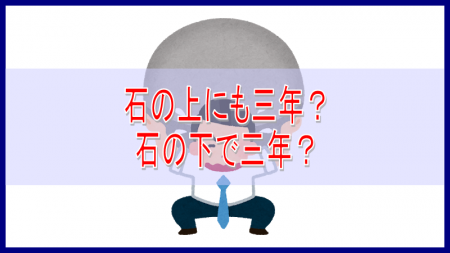オープニングスタッフがたくさんいる職場が苦手です。
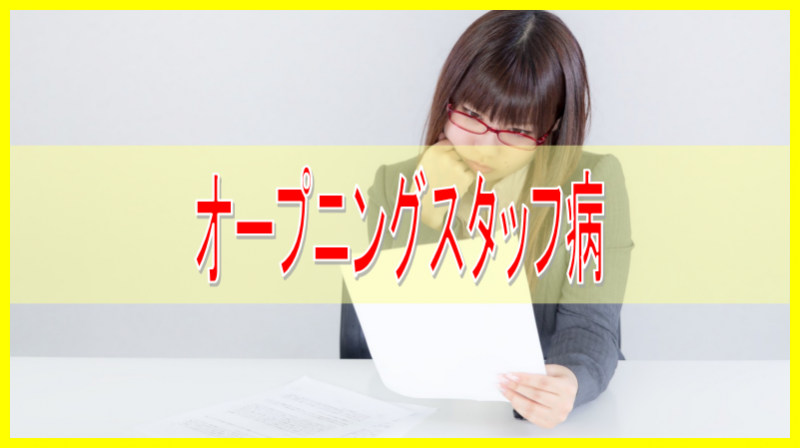
オープニングスタッフ病と私が勝手に呼んでいるものがあります。
ここでは小さな喫茶店をオープンした、と仮定して書き進めます。
物語にしてみた
会社の新プロジェクトとして異業種の喫茶店運営をやることになりました。
居抜き物件が見つかり、早速喫茶店をオープンすることとなりました。
会社から適任と思われる人が選ばれて彼らがオープニングスタッフとなりました。
大まかな方針、メニューは会社が決めてはくれましたが、看板、内装、イスの種類、各種業務フロー、メニューリスト作成など、たくさんのことを手探りで決めていかなくてはいけません。
残業、休み返上、持ち帰りもありましたが、モチベーションで乗りきることができました。
オープンしてからトラブルの連続でしたが、少しずつ「型」が構築され、業務が円滑にすすんできました。
「おれたちの喫茶店だ!」
日に日にそんな思いが強くなっていきました。
オープンから1年ほど経ってから、おつりとレシートは同時だすか、先におつりだけ渡してレシートはあとから出すか、ということでスタッフ2人が口論になりました。
どちらもその喫茶店を愛し抜いている2人です。
- どっちでもいいじゃん?
- 他のスタッフを含めて多数決採れば?
- どちらにしてもそんなにムキになる必要はなくない?
そんな意見は言える雰囲気ではないです。
店長がバシッと決めて!とスタッフ皆が思いましたが、店長は意見をなかなかいってくれません。
店長はどちらの人も否定したくなく、自分が嫌われたくもなく、また、店長といっても「仕事歴は全く一緒」ということも頭にありました。
言い合いを重ねて「もうやってらんねー」と1人は退職してしまいました。
他のスタッフは言い合いをしたスタッフよりも店長に対して不信感を抱くようになりました。
そして、退職したスタッフの穴を埋めようと新しく人を採用しました。
採用されたA君は頑張ろうと思っていたのですが入社して数日で嫌気がさしてしまいました。
理由は、効率の悪い業務フローが構築されてて、そのやり方を全員が信じて疑わず、さらには全員が楽しげに残業や休日出勤をすることで効率の悪さをカバーしていたからです。
意見を言える雰囲気はなく、A君は「これはついていけない」と感じました。
店長に相談すると「仕事とはそういうものだ」「給料の対価分の仕事をできているのか」「お客様の笑顔を思い出せ」などと言われ、また別のスタッフに相談をしても同様でした。
「僕はただ普通に喫茶店で仕事をしたかっただけなのに」
そうして、A君は退職をしました。
ほどなく、A君の穴を埋めるためB君が採用されました。
しかし、A君と同じ理由でB君も退職しました。
採用すればやめる、を繰り返し、気づけばオープニングスタッフ以外、長期勤務している人はおらず、いつまでたっても人が定着しないままです。
そんな中、オープニングスタッフと同じ熱量で仕事をこなす待望の新人F君があらわれました。
「最初は戸惑ったけど、今は僕もみなさんに負けないくらいこの仕事が好きです」
そして、F君は安月給にも関わらず残業、サービス勤務を繰り返しました。
すっかり1人前になったF君に、新人教育をお願いしました。
新人G君が採用され、F君は一生懸命「自分の分身」になってくれるように教育しました。
すると、G君が「ついていけないです」と弱音を吐くようになりました。
F君はG君に辞めないように説得しました。
「仕事とはそういうものだ」「給料の対価分の仕事をできているのか」「お客様の笑顔を思い出せ」
そんな言葉も虚しく、ほどなく、G君は退職しました。
それからしばらくしたある日、F君とオープニングスタッフのSさんがテーブルの拭き方について言い合いをはじめました。
- どっちでもいいじゃん?
- 他のスタッフを含めて多数決採れば?
- どちらにしてもそんなにムキになる必要はなくない?
そんな意見は言える雰囲気ではないです。
店長がバシッと決めて!とスタッフ皆が思い、そこで店長は社歴の長いSさんの意見を採用しました。
「こんなに一生懸命仕事しているのにそんな扱いかよ」
そう思ったF君は仕事を辞めてしまいました。
オープニングスタッフ病
軽い気持ちで書き始めたら長くなってしまいました汗
バイトを含めた私の仕事の経験の中で、どこでも当てはまるのが「オープニングスタッフがいるとやる気ありすぎて後続がついていけない」というものがあります。
そりゃ、生みの親みたいなものですから会社が子供のように感じたりもしますし、無理もないことです。
しかし、先輩がいないですから謙虚になりにくく、自分達で構築したやり方ですから愛着があり、そこから離れることが困難になります。
当然客観的になれなくなり、盲目的になります。
その足らない部分(効率の悪さ)を人力(モチベーション)でカバーするわけです。
以前にモチベーションで仕事はできないという記事にも書きましたが、仕事が好きな人が業務を組むとロクなことがないです。
なぜなら好きだから「時間短縮しよう」「早く帰ろう」が頭にないからです。
そして、前述の例で言えば「喫茶店で仕事したいな」という程度の志望動機の人に、効率の悪い業務をさせて「常に仕事のことを忘れるな!」という精神論を押し付けても無理ゲーです。
後続のスタッフは、極々一部の超意識高い系か「そっか、仕事ってこういうものなんだ!」という素直な(または思考停止の人)以外は勤続は不可能です。
別名、ベンチャー企業病
このオープニングスタッフ病はベンチャー企業だとかなりの数の会社があてはまるのではないでしょうか。
まさに例として書いた物語のようになり、社歴が5年以上チームと2年未満チームに別れ、真ん中はざっくりといない会社も多いでしょう。
私が以前に勤めていた会社もまさにこんな感じでした。
「なんであんなに頑張れるんだ!?」と不思議なくらいでした。
今にしてわかるのは、頑張れるのは彼らがオープニングスタッフ(創業メンバーまたはそれに準ずるメンバー)または素直な(または思考停止の人)だったからです。
さらに、彼らは夢をもっています。
「夢をもっている」オープニングスタッフは最強です。
どこまでも前向きにがんばれますから。
当然、ほとんどの一般人はついていけません。
一般人の私は例外なくこちらです。
・・・と、毒づいた感じになってしまいましたが、それでも彼らを尊敬しています。
なぜか?
彼らのような異次元の働き方をする人達が世界を変えていくと思うからです。
淡々と飄々といい感じにうまくやりたい
なんでこんなことを書こうと思ったかというと、勤務する会社で新規プロジェクトがはじまり、オープニングスタッフ病にかかる人が続発しているからです。
プロジェクトが始まる前に「オープニングスタッフ病にかかるからマジで気を付けて」とリーダーに伝えていたのですが、結果は前述の物語のようになりました。
普段なら冷静な対処ができるはずの人も新規プロジェクトの件になると、愛があるために冷静でいられず、小さなことで言い合いがはじまり、退職する人がでて、新しく採用するもついていけない新人は脱落し、いった具合です。
人が安定しないため、今度は私がそれを緩和(?)する役を命じられました汗
まずは業務フローをスリム化して、入れ込みすぎているスタッフにはその熱量を周りと同じくらいに「落として」もらう予定です。
そんな私もバンドをやっている頃はバリバリのオープニングスタッフ病でした。
他のメンバーのやる気が足らない、ということをよく思っていました。
しかし、今ならそりゃそうだろ、とも思います。
- バンドの創設者で、バンド名を決め、バンドメンバーを集め、曲をかき、ギターを弾く人
- 途中から参加し、ベースを弾いている人
この2人がバンドにかける気持ちが同じになるわけがありません。
今にして思えばもっと気を抜いてやっているべきだったなぁ、その方がうまくいっただろうなぁ、と思います。
また、「バンドは小さな会社」だったと実際に会社員になってからよく思います。
そうした経験を経て私が行き着いたのが「淡々と飄々といい感じにうまくやる」です。
※このblogのサブタイトル
今回、会社から命じられた「緩和させる」ことも淡々と飄々といい感じにうまくやれればと思います。