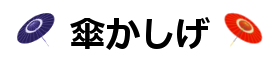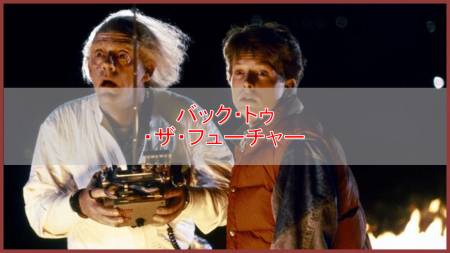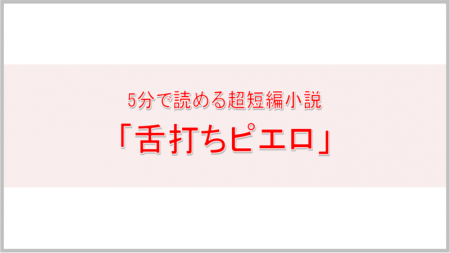MTRの名機 KORG D16の思い出を語ってみた

結構前に「パソコン、オーディオインターフェース、DAWを買い替えた!」のですが、仕事やら何やらでなかなか触れていません。。
そして、触る気にならない要因の1つに、トラブル多すぎ!ということがあります。
これはオーディオインターフェースのせいなのか?abilityのせいなのか?など、「非音楽的時間」がストレスで、早くもすっかりやる気を失いつつあります汗
で、
1台完結の音楽制作専用機はないものかと探したりもしたのですが、ないものですねぇ。。
楽器メーカーさん、だしてくれないかなぁ。売れると思うんですが。。
調べた中では「JUNO-Gi」が近いですが、マウスとモニタがやっぱりほしいなぁ。。
■参考サイト
【BARKS編集部レビュー】ギタリストにお勧めしたいデジタル・レコーダー内蔵のモバイル・シンセサイザーJUNO-Gi
MTRに戻る人もいる
あれこれネットで見ていると、私のように「トラブル疲れ」からMTRベースの制作に戻る人もいるようです。
気持ちはすごくわかる。特にバンドサウンドならそれでほぼ問題はないですから。
あとは「限界がある中で音楽を作りたい」というもの。
これも超わかる!PCベースだと何でもやれますし、シンセの音選びだけでも膨大にありすぎてえらく時間がかかります。
私はD16(MTR)とPOD(ギターアンプシミュレーター)とTriton LE(シンセ)で作業してましたから、限界ありまくりの中でやってました笑
でも、その方が1つのことに工夫をしますし、作業には時間がかかるものの「なんだかわからないトラブルの原因探す時間」は皆無でした。
で、
「D16に戻ろうかなぁ。。」と思いました。
・・・ということで、「私とD16」と題して、思い出を書いてみます。
KORG D16とは
まず、D16について簡単に説明します。
- 1999年11月発売
- 発売当初は20万円くらいした
- 今はメルカリで中古が5000円くらい
- 16bit時、同時再生16トラック、同時録音8トラック
- 24bit時、同時再生8トラック、同時録音4トラック
- Hi-z端子入力端子あり
- 一通りのエフェクターはある
- ファンタム電源はない
- ムービングフェーダーではないが、音量をここで下げる、などの設定をすることができる
- SCSI端子装備でCDドライブを付けられる
- 16トラックをパラでWAVデータで書き出せる
- 備え付けのHDDは2.1GBだけど、自分で改造すれば40GBのHDDにできる
音質の細かいところを突っ込まなければ、バンドでのセルフレコーディングくらいなら今でも全く問題なく使えます。
D16との出会い
ミュージシャンを目指して上京してきた友達が、音楽を辞めて地元に帰るとのことで、格安で買わせてもらいました。
それが、2000年頃立ったと思いますが、それからは途方もない時間をD16と過ごしました。
世界一、D16を使ったと思います笑
ちなみに、後述するの中田ヤスタカ風サウンドのボーカル録音もD16です。
WAVで書き出せるのは素晴らしい限り!
傘太郎の当時の使い方
- パソコン(ssw)でドラムとメロディーをMIDI打ち込み
- Triton LEのMIDI INに繋ぎ、Triton LEを鳴らし、オーディオでD16に流し入れる(曲の長さと同じ時間×トラック数待たないといけない)
- 流し入れるときはトリガー録音(MTC同期できるが結局音がずれるので)
- ドラムとメロディーのトラックをそれぞれD16のメトロノームの頭に揃える(耳で合わせるので面倒だし、完全ジャストではない可能性もある)
- そこにベースをライン録音
- PODを介してギター録音
- シンセのウワモノをsswでMIDI作成
- メロディー、ドラムの時と同じ要領でTriton LEのストリングスやブラスなどのオーディオをD16に流し入れる
- 同様に頭を揃える
- SM58をD16に突き刺してボーカルレコーディング
- 複数ボーカルトラックのセレクトとそれらを1トラックにまとめる
- ストリングスのクレッシェンドやボーカルの大小、エフェクターなどを各トラックごとに編集(パソコンでやるよりかなり大変)
- 各トラックがまとまったら新規ソングにコピペ(ここから全体のミックス。私は制作用とミックス用でわけるようにしています)
- 「ドラム&ベース」「ボーカル&コーラス」「ギター全部」「シンセ全部」の4つに分ける
- 上記の4つを音量バランス、EQを整えて、カラオケを2MIX
- カラオケの2MIXをボーカルが一番出ている周波数帯域をEQで削る(ボーカルが聴こえやすくなるので)
- EQ済みのカラオケとボーカルをmixして完成
- 最後にマスタリングエフェクトをかける
ざっくり言えば、PCでMIDIをつくり、シンセはパラで流し入れて、ギター、ベース、ボーカルはMTRに直でオーディオ録音、というところですね。
一昔前はみんなこんなでしたが、シンセ音が増えたらこのやり方はかなりきついです。
それこそ先日作ってみた中田ヤスタカ風サウンドをMTRで作るとなるとかなりきついです。
ABILITYPROのみで作り、LANDRでマスタリングした曲を公開!
最大の利点はトラブルの少なさ
でも、このやり方だとトラブルは本当にないです。
面倒な作業も「音楽的な時間」であり「少しずつ完成に向かっている時間」なので、凌げるんですよ笑
PCベースの音楽制作が当たり前になった2011年頃にこのやり方で作った曲で某事務所の作曲家オーディションに合格しました。
「MTRで作った」と言ったら超驚かれましたが笑、つまり、クオリティもクリアなんですよ。
※いつか上記のやり方で作った曲もアップしたいと思います。
前にDTMのためだけにパソコンを買うことに。もうそれなら音楽制作専用機が欲しい!でも書きましたが、ソフトシンセも入っているMTRがあったら売れると思うんだけどなぁ。
まぁ、今はもうipad+garagebandがそれにあたるか。
スマホでも作れるわけで、そりゃMTRを欲しがる若者はいないか。。
MTRをこよなく愛した者としてはちょっと寂しいですね。。