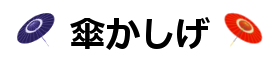黒子のバスケ脅迫事件の最終意見陳述は、最高の育児書!

前回、子育てはラジオに良いのか悪いのかについて書きましたが、付随して子育てについて書きます。
私の中で育児書としてすごく良書だと思うのが、渡邊博史氏の黒子のバスケ脅迫事件の最終意見陳述です。
ポイントとしては巷にたくさんある「立派に子供を育てたお母さんが語る子育ての仕方」ではなく「子育てに問題があり社会に適応できなくなった子供が大人になってから幼少期の体験を分析している」点です。
「学力をあげる」「運動神経を良くする」とかではなく「前向きで明るい人生を過ごせる人にする」ためにどうしたら良いかが書いてあり、当事者自ら「こうやったら俺みたいになるからダメだぞ」と教えてくれています。
死刑制度、オタクなど、内容が多岐にわたり、本1冊分くらいの長さですが、一読の価値があります。
特にお子さんがいる方は読むことをおすすめします。
言葉のセンス、達観した視点、物事を説明する手順のよさ、分かりやすい比喩など、その文才は目を見張るものがあり、ピックアップしたいことはたくさんなのですが、ここでは育児に特化して書いていきます。
育児書としての観点で一言でまとめると
- 子供に安心感を与えること
はじめは3行にまとめようと思っていたのですが、この1行だけでした笑
つまりこの供述は「安心感が持てなかった理由、そのために生きていくのが大変だったこと、その果てにわかったこと」が書いてあり、終止自虐的な内容が続き「私のような人が増えないように」と言ってます。
抜粋していきます。
乳幼児期に両親もしくはそれに相当する養育者に適切に世話をされれば、子供は「安心」を持つことができます。例えば子供が転んで泣いたとします。母親はすぐに子供に駆け寄って「痛いの痛いの飛んで行けーっ!」と言って子供を慰めながら、すりむいた膝の手当をしてあげます。すると子供はその不快感が「痛い」と表現するものだと理解できます。これが「感情の共有」です。子供は「痛い」という言葉の意味を理解できて初めて母親から「転んだら痛いから走らないようにしなさい」と注意された意味が理解できます。そして「注意を守ろう」と考えるようになります。これが「規範の共有」です。さらに注意を守れば実際に転びません。「痛い」という不快感を回避できます。これで規範に従った対価に「安心」を得ることができます。さらに「痛い」という不快感を母親が取り除いてくれたことにより、子供は被保護感を持ち「安心」をさらに得ることができます。この「感情を共有しているから規範を共有でき、規範を共有でき、規範に従った対価として『安心』を得る」というリサイクルの積み重ねがしつけです。このしつけを経て、子供の心の中に「社会的存在」となる基礎ができ上がります。
何気ない文章ですが、こんなに分かりやすく説明できる人はそうそういないでしょう。
そして、安心感を与えることで子供は「1人じゃないんだ」と思うようになると続きます。
↓
またこの過程で「保護者の内在化」という現象が起こります。子供の心の中に両親が常に存在するという現象です。すると子供は両親がいなくても不安になりませんから、1人で学校にも行けるようになりますし、両親に見られているような気がして、両親が見てなくても規範を守るようになります。このプロセスの基本になる親子の関係は「愛着関係」と呼ばれます。
他の本で読んだことがありますが、親が愛情をたっぷり注いだ(愛着関係の)子は常に「1人じゃない」という意識があるため、悪事に手を染めることがなく、勉強であれなんであれ「1人だけでやっている」感覚ではないので、何事も前向きに楽しめる傾向があるそうです。
親に愛されまくった友達を見ていると本当にその通りです。
では、愛着関係にならないしつけ方とはどういうものでしょうか。
↓
子供が泣いていても母親は知らん顔をしていたとします。すると子供はその不快感が「痛い」と表現するものだと理解できず「痛い」という言葉の意味の理解が曖昧になり「感情の共有」ができません。さらに母親から「転ぶから走るな!」と怒鳴られて叩かれても、その意味を理解できません。母親に怒鳴られたり叩かれるのが嫌だから守るのであって、内容を理解して守っているのではありません。さらに「痛い」という不快感を取り除いてくれなかったことにより、子供は被保護感と「安心」を得ることができません。母親の言葉も信用できなくなります。感情と規範と安心がつながらずバラバラです。そのせいで自分が生きている実感をあまり持てなくなります。
かなり重いですね。
ここで言う「自分が生きている実感」は、思春期あるあるの「僕はなんで生きているんだ!」というものとは異なる、もっとどっしりと重いものを感じます。
すでに70なのに「なんで90じゃないんだ」というのが通常の思春期ですが、この場合は0が1にできない苦悩のように感じます。
根幹から違っているというか。
本当にきついでしょうね。
ちなみすでに70なのに90じゃないことを嘆く人達は尾崎豊を聴きがちです。(私はもれなくこちらでした笑)
渡邊氏は自分をこう語ります。
↓
「安心」が毀損しているので常に萎縮しつつ、何をやっても本気で楽しいとも面白いとも思えず虚しいばかりという自分の人格が形成されました。
(中略)
子供はよほど酷い身体的虐待でも受けなければ「愛してくれなかった」と認識できません。自分もそのようなことは考えませんでした。ですから「愛してくれなかった」ことにより無意識裡にその後の行動に大きな悪影響が与えられていることにも気がついてません。
「子供は目の前の異常に気がつかない」
という、教育における一番恐ろしい点を指摘していますね。
小さいことで言えば「朝食はどの家でもパンを食べるものだと思ってた!」というようなことであったりするわけですが、渡邊氏の場合の一例を取り上げると
自分の小学校の卒業遠足はディズニーランドでしたが自分は参加していません。風邪をこじらせて寝込んでいたからです。母親は自分に「遠足の積立金がもったいない」と繰り返しましたが「遠足に行けなくて残念だったね」とは一言も言いませんでした。このようなことが乳幼児期から積み重なると「遠足が楽しい」という感情を持てなくなるのです
両親はいつもよい結果を無視し、悪い結果には怒りました。自分にとって努力とは怒られるなどの災禍を回避するための行為であり、努力の先に報いがあるとは思いもしませんでした。
これらを「親の普通の対応」と誤認して大人になったわけです。
これを明確に「ひどい親だ」とわかればまだ救われますが、子供にはわかりません。
「世の中はそういうものだ」「自分はそういう存在だ」と子供は納得するしかありません。
そうしたらしたら、未来はただただ暗いものになります。
そして虐待についても語っています。
虐待について
虐待についても申し上げます。「虐待」という言葉は英語のabuseの訳語abuseの本来的な意味は「濫用・乱用」です。drug abuseは「薬物乱用」です。ですからchild abuseの正確な翻訳は「子供乱用」です。虐待の本質とは「両親が自身の欲望の充足のために子供を乱用する」ということです。自分は「虐待の本来の意味は乱用」という理解が社会に共有されることを切に望みます。この理解が社会に共有されないと、日本人が子供が死に至るまでの身体的虐待かネグレクトしか虐待として認識できない状態がいつまでも続きます。
唸るほどの説得力です。
「子供は英語を喋れるようにしたい」という「己の欲」を「子供の将来のために」にすり替えて、嫌がる子供を英会話教室にぶちこんで、自分は努力はせずに子供には努力を強要させている親御さんも「乱用」と言っても過言ではないでしょう。
「は?私のしていることが子供に悪影響?ふざけないでよ!子供を愛しているからやっていることよ!」と、親は「愛情を注いでいる気分」になり、子供には感情の共有がされず、辛いだけです。
言い換えるなら、愛情があってもそれが一歩通行で、親の充足感満たすだけになっていたら「乱用」にあたるでしょうね。
そう考えると子供を乱用している親はたくさんいそうです。
ネグレクトについてはその線引きが巧みな比喩で説明されています。
「心理的ネグレクト」という虐待カテゴリーの存在を広く社会に認識して頂きたいと思います。通常のネグレクトとの違いを説明します。子供が病気になっても両親がそれに気がつかず病院に連れて行かないのがネグレクトなら、病院に連れては行くが全く心配をせず「大丈夫かい?」の一声もかけないのが心理的ネグレクトです。充分な食事を与えないのがネグレクトなら、食事を与えても餌を与えるかのように出し「美味しいかい?」の一声もかけないのが心理的ネグレクトです。
親が忙しいと「風邪?薬はそこ入ってるから」「お腹すいた?その辺のもの食べといて」となりそうですが、これもたまには仕方ないにしても、毎回にならないように、心ない対応にならないように、気を付けたいものです。
両親との心理的な交流がないと子供は何が好きで、何が美味しくて、何をガマンしないといけないのかが、よく分からないままに育ってしまいます。つまり自分の意志を持つことが困難になるのです。これが「心理的ネグレクト」です。これを受けた子供は原因を把握できないまま物凄い生きづらさを抱えることになってしまいます。
かるーーくですが、私自身この傾向があったので、渡辺被告の文章に魅かれるのかもしれないです。
両親が忙しく鍵っ子だった人の半数以上は、かるーーくこの傾向があるんじゃないでしょうか。
そして最後に長文をこんな言葉で締め括っています。
日本中の前途ある少年たちが「安心」を源泉に「生きる力」を持って、自分の意志を持って、対人恐怖と対社会恐怖に囚われることなく、前向きに生きてくれることを願って終わりにしたいと思います。
まとめ
原文が凄すぎて解説が難しかったですが、冒頭にも書いた通り、まとめると一言です。
- 子供に安心感を与えること
そのためには
- 子供を乱用しないこと
- 感情の共有をすること
この2点に集約されていると感じました。
最後に
私はこの文章を読んだのは独身の頃でしたが、自分が親になったら必ずもう一度読むと決めていました。
それぐらい私には響く文章です。
「響くか、響かないか(わかるか、わからないか)」について、渡邊氏はこのようなことを述べています。
自分がこれから説明をしましても大半の人は、「喪服が心神耗弱による減刑を狙って『生霊』とかほざき出したwwww」「「悪魔に体を乗っ取られた」とか「ドラえもんが何とかしてくれると思った」とかの方が言い訳として面白いよ」というような感想しか抱かないと思います。そのような感想を抱いた人は、それがご自身が真っ当な人生を歩んで来た証拠ですので喜んで下さい。これから自分が申し上げることが少しでも分かってしまった人は、自分と同じような生きづらさを抱えている可能性が高いです。ですから自分はこの最終意見陳述について「で、それが何?」という反応が大多数を占めることを心から望んでいます。
「で、それが何?」という人達は良いよなぁ、と私も思います笑
個人的には、渡辺被告には残りの人生を正しい自己認知を持てたことを喜んで、前向きに楽しんで過ごしてほしいです。